「お東さん」「東本願寺さん」と親しく呼ばれている東本願寺、正式には「真宗本廟」と言いますが、京都駅を降り立つと、その大きな伽藍が目の前に広がります。
ただ、この10年ほど、宗祖親鸞上人、七百五十回御遠忌記念事業として、平成の大修理が順次行われていて、その大きな伽藍を工事用の素屋根が覆っていて、全容を見ることが出来ないのが残念です。
平成16年(2004年)に始まった御影堂の大掛かりな修復も、平成21年(2008年)に無事完成し、再びその美しい姿を現しています。
そして翌年、引き続き阿弥陀堂と御影堂門の修復が始まり、来年平成27年(2015年)には完成する予定です。
過日、御影堂の屋根の修復現場を見せていただきました。
修復工事のパンフレットです。
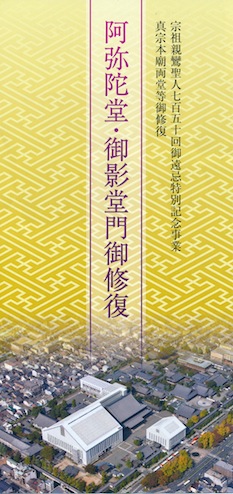
烏丸通りに面した、阿弥陀堂門です。

阿弥陀堂門を入ると、目の前に阿弥陀堂を覆う、工事用の素屋根が大きく広がります。
この素屋根は、北側に位置した御影堂工事の素屋根を終了後、そのまま南方向にスライドして、御影堂に再利用しています。
素屋根は、間口92メートル、奥行79メートル、高さ51メートルという巨大なものです。
環境への配慮から、雨水の再利用、太陽光パネルの設置などの工夫を凝らしてあります。

階段を上がると、素屋根一階部分となります。
仮設の工事用の素屋根は、工事が完成すれば不要となるものですが、長期に亘る工事中の建物を保護、風雨、塵埃、騒音を防ぐ事はもちろん、工事の安全を守るために不可欠なもので、多額の費用を掛けた大規模な構造に驚きます。

工事用出入口のある、素屋根南側全景です。
左側には工事用資材などが整理されて置かれています。

エレベーターで3階まで上がると広々とした空間になり、見学者が自由にそこから工事を見ることができます。
御影堂に比べて、阿弥陀堂は小さいので、工事用のスペースもゆったりした感じがします。

既に屋根の瓦葺きも大半が終わり、大棟の工事中のようです。


破風周りの工事が行われています。

錺金物などが光っています。

2階では多くの工事従事者が働いています。

3階の窓から西山方面を眺めると、堀川通りに面した、西本願寺の伽藍が見えます。

素屋根3階のテラスに出ると、完成した御影堂の屋根部分が目の前に広がります。
古い瓦で再利用出来るものは、雨があまり当たらないような場所に使用し、また粉末にして、新調瓦に混入したりして、出来るだけ廃棄処分を少なくするよう、心掛けておられるそうです。

反り屋根の流れが美しく見る事ができます。

降り棟、隅棟、と美しい流れが見られます。

降り棟の正面の獅子口も美しいです。

流れるように降り棟から、隅棟、稚児棟と治まって、屋根の美しさを改めて感じることが出来ます。

破風部分です。
破風板や懸魚には錺金物が美しく映えます。
この錺金物は、取外して再利用出来るものは、錆を落とし、金箔を張替えて美しい輝きを取戻し取付けてあります。
このような機会でしか破風廻りなど、近くから見ることができません。

拡大して見ています。
大棟獅子口と隅巴瓦、そして破風部分と手の込んだ仕上がりです。

大棟の実物の大きさの展示です。

「毛綱」が展示されています。
明治13年(1880年) 御影堂、阿弥陀堂の再建工事は難渋を極め、用材を引く綱が切れたりしました、その時、多くの女性の髪の毛と、麻を撚り合わせて編まれたのがこの毛綱です。
両堂、再建への熱い想いと、多くの人々の無償の働きによって、再建されたもので、その記念として展示してあります。

東本願寺撞鐘(梵鐘)が展示してあります。
慶長7年(1602年)徳川家康から寺地の寄進を得た教如上人が、同9年(1604年)9月の御影堂の造営に合わせて鋳造したものです。
高さ256センチ、口径156センチ、重量3800キロです。

中央「池の間」には、飛天の図柄が見られます。

梵鐘を吊下げる竜頭部分です。

本願寺と彫込まれた、古い瓦が工事現場の隅に集積されていました。

素屋根1階から、御影堂門の素屋根が眺められます。
阿弥陀堂と共に、来年度はその美しい姿を再び見せてくれることでしょう。

完成なった、美しい「御影堂」全景です。

御影堂の廻廊です。

御影堂
世界最大の木造建築で、宗祖親鸞上人の御真影が安置されているところから、御影堂と呼ばれています。
正面高さ76m、側面高さ58m、高さ38m、瓦数175.967枚、畳数927枚です。
阿弥陀堂
ご本尊阿弥陀如来を中心に、その左右に聖徳太子をはじめ、七高僧の御影がおかれています。
正面高さ52m、側面高さ47m、高さ29m、瓦数108.392枚、畳数401枚です。
(パンフレットより転載しました)

コメントする