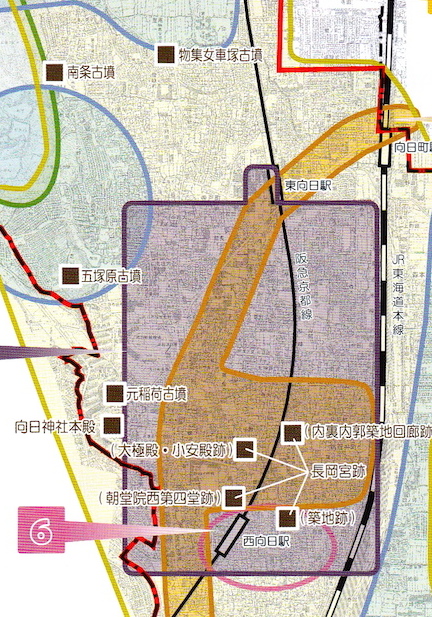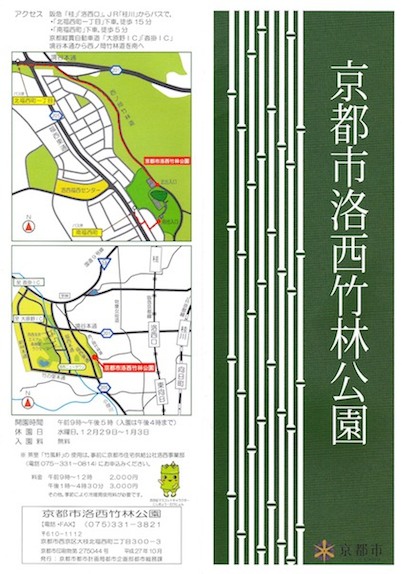江戸時代の重要な街道の一つであった西国街道、京都の東寺口から摂津西宮まで、向日市、長岡京市、高槻など淀川右岸を通り西宮まで、さらに中国九州の西国へと続き、近世から近代まで陸上の大動脈として、文化社会産業の発展に大いに寄与してきました。その西国街道は、向日市では古くから町の発展に貢献し、街道沿いに多くの史跡や建造物が残されています。
JR向日町駅前の整備に伴い、新しく寺戸川の「深田橋」畔にモニュメントが設置されました。その内の説明板です。
「深田橋」畔のモニュメントです。


阪急東向日駅前の「築榊講常夜燈」(つきさかこうじょうやとう)のある場所ですが、現在整備中で移転し、工事が済み次第、元の位置に設置されそうです。天保13年(1842年)の建立で、西国街道を往来する人々の安全を見守っていました。
「向日町道路元標」大正9年(1920年)に設置された道路元標です。町の中心部に設置され、道路の起点として市町村間の距離標示の原点となったものです。

「須田家住宅」京都府有形文化財です。「向日町道路元標」のそば、街道沿いに建っています。屋号を「松葉屋」といい、醤油を製造販売をしていました。この辺りには同じような商家が数多くあります。
古い町並みの名残が処々にあります。
「富永屋」です。玄関横に説明板が取付けられています。
「富永屋」の外観です。富永屋は江戸時代始めから戦後しばらくまで、宿屋、料理屋を営んでいました。江戸中期に建てられた貴重な町家です。
「向日神社」です。平安時代の「延喜式神名帳」にも記載される格式の高い古社で、養老2年(718年)に建立されたと伝えられています。中世の向日神社は村の守り神として地域の象徴として畏敬を集めてきました。向日という地名のもとになった神社です。
「西国街道」に面した参道の「大鳥居」です。
大鳥居の左側の「説法石」です。鎌倉時代末期に「日像上人」が、京での布教活動を禁じられ、洛外追放によりこの地でこの石の上から人々に説法したと伝えられています。
「大鳥居」を潜ると緑の濃い石畳の参道が長く続いています。
長い石畳の参道の奥には、正面には「舞楽殿」が見えます。
参道の途中、右側には「勝山稲荷神社」があります。商売繁盛の神様です。

「本殿」です。
「手水舎」です。18世紀後期に建てられました。
参道正面に建つ「舞楽殿」です。
「舞楽殿」です。奥に「拝殿」が見えます。
「拝殿」です。桁行約9m梁行約3.6m入母屋造りで屋根は向唐破風、檜皮葺きという格式ある形です。
「拝殿」の奥に「本殿」があります。向日神、玉依姫命、神武天皇をお祀りしています。
「天満宮社」です。天保四年(1833年)建立されました。学業成就の神様です。
「春日社」です。弁財天、身代不動尊をお祀りしています。
水上勉の「桜森」の舞台となったと言われている「桜の園」からの「元稲荷古墳」を経て、向日神社への参道の鳥居です。

桜の参道として静かな参道です、左に元稲荷古墳(勝山公園)が広がっています。

「向日神社御旅所」です。上植野町西小路にあります。「向日神社」の例祭の「神幸祭」ではこの地まで鳳輦や鉾など行列が氏子地域を回ってきます。
「神輿」が鎮座されます。
街道沿いの「南真経寺」(京都府文化財)です。鎌倉末期に「日像上人」の布教により村人が日蓮宗に改宗した信仰の中心です。かって天正末期(1590年)日尭が開いた鶏冠井興隆寺(かいでこうりゅうじ)と呼ばれる東西120m南北140mの広大な境内を持つ寺院でしたが、江戸初期に僧侶の学問所「壇林」を開講するため、南北両真経寺に分割されました。
「山門」です。
「開山堂」(京都府文化財)です。入母屋造りの瓦葺きの建物です。内陣には「日像上人像」と「十界曼荼羅」が安置されています。
「本堂」(京都府文化財)です。宝形造りの瓦葺き屋根で正徳4年(1714年)に建立されました。柱が外側に立っているのが特徴です。
「北真経寺」です。正式名称は、日蓮宗「鶏冠山真経寺」です。承応3年(1654年)真経寺を南北に分けて鶏冠井壇林を開き、北真経寺を学問所に、南真経寺を宗教活動の場としました。明治以降は一般の宗教活動の場となりました。山門です。
「本堂」(旧の講堂)です。
「鐘楼」です。

「妙見堂」です。
「南門」です。
正面に由緒の銘板が置かれています。
向日市鶏冠井町の西国街道沿いの「石塔寺」です。鎌倉時代末期、日像上人が向日神社前「法華題目」の石塔のそばにお堂を建てたのが始まりと伝えられています。毎年5月3日の花まつりの「鶏冠井題目踊り」は京都府の無形民俗文化財に指定されています。
「山門」です
手入れの行き届いた広い庭園の奥に「本堂」があります。
「鐘楼」です。
「石塔寺」を出て、五辻の信号から西国街道を「一文字橋」に向かうと、歴史の道として雰囲気を感じさせる石畳の道となり、街道筋らしい風致を残し保存している様子が窺えます。
「街灯」が所々に設置され夜は燈が灯るようです。

街道筋の左右に往時の面影を留める民家が並んでいます。
虫籃窓や犬矢来のある旧家が見られます。
中小路家住宅(国登録文化財)です。江戸から明治時代の旧家です。
「中小路家住宅」です。
向日市の南端、長岡京市に接する「一文字橋」です。橋の袂に西国街道と一文字橋のモニュメントが設置されています。
「一文字橋」の由来です。(京と摂津西宮を結ぶ西国街道の小畑川にかかるこの橋は、室町時代ごろから有料の橋都も伝えられる、大雨のたびに流されその架け替え費用のため通行人から一文を徴収したのが橋名の由来といわれる。)
橋名には「一文銭」のモニュメントが設置されています。